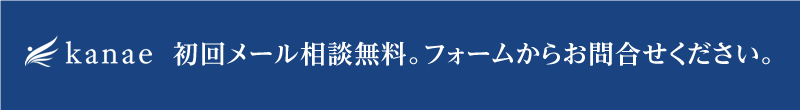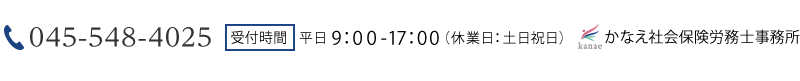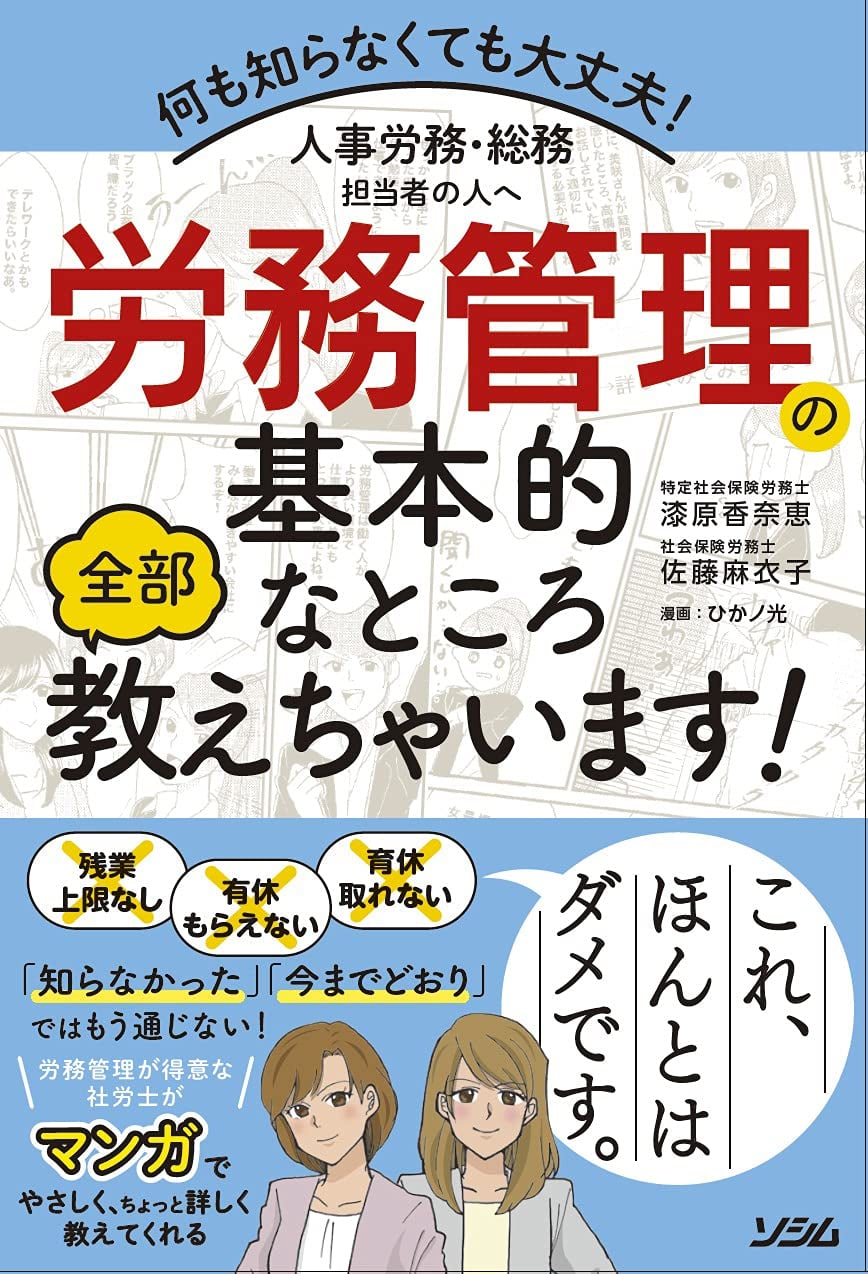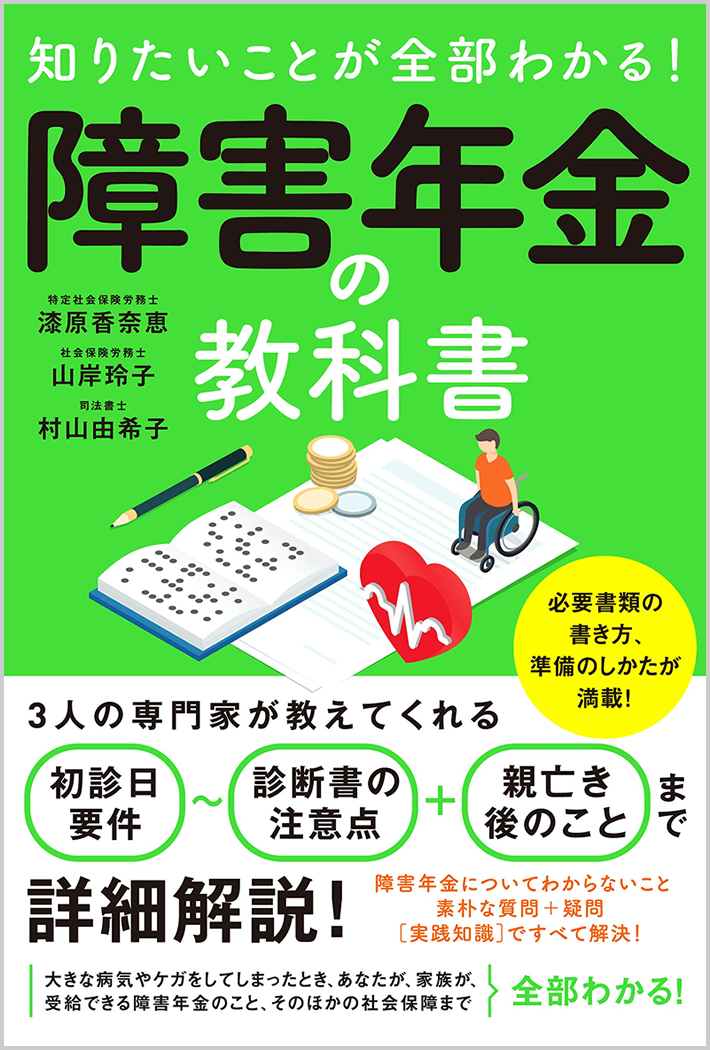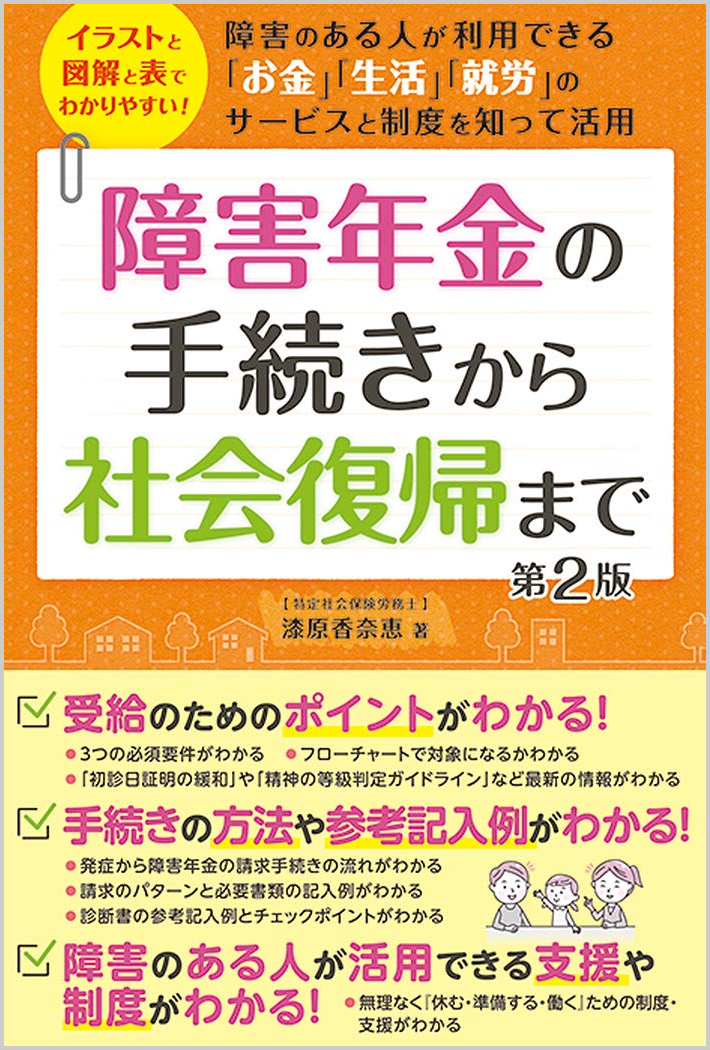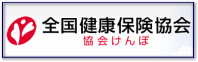就業規則には、働き方のルールを明確にして労使トラブルの防止や解決の基準になるという重要な役目があります。
就業規則が適正にはたらくこと、下記のような効果があります!
就業規則は経営の道標となります。
↓
会社の労務管理が円滑に行われます。
↓
職場の雰囲気が良くなります。
↓
業務の効率化や従業員のモラール向上が実現されます。
↓
そして、結果的には会社の収益力アップにもつながってきます。

事業主と従業員の間の労使トラブルは年々増加する傾向にあります。
終身雇用制や年功序列で賃金が保証されていた時代には従業員の会社への愛社心も高く、会社を訴えるような事例も現在に比べれば多くはありませんでした。
しかし、現在では終身雇用が崩れ、従業員が自立するようになり、愛社心や義理人情の関係にこだわらない若い世代が増える中、思いもよらない要求をされる可能性もあります。
もし、配転・退職・解雇や時間外手当、賃金・賞与などについてトラブルが発生した場合や、上記のような問題社員を雇ってしまったときにしっかりした就業規則のルールが無い中で処分を課したりすると、逆に会社が訴えられる危険性もあるのです。
就業規則で労働者の労働条件や遵守すべき職場秩序が明確になっていれば、ルール違反は一目瞭然ですし、その就業規則により懲戒を行うことも可能です。
また、曖昧な部分を多く残しておくと、お互いに都合の良いように解釈してしまったり、甘えが生じたりし、後々気持ちのいい関係を保てなくなることもあります。
強い組織にするためには、現場に即した就業規則を定めることが必要です。
当事務所では、社長様とヒアリングを重ね、会社ごとの実情に合わせた就業規則をオーダーメードで必要事項を中心にまとめたシンプルな就業規則から、労使のトラブルを回避する就業規則、社員のモチベーションを高める就業規則まで作成します。
こんな就業規則は見直しが必要です!
こんな就業規則は危険な可能性があります!
- 何年も見直しをしていなくて、法改正に対応できていない
- インターネットで無料で配布されているテンプレートの就業規則をダウンロードしてそのまま使用している
- 同業他社や関連会社の就業規則を真似て作成した
- 実際の運用と規程とにズレが生じている
- 法律的な用語が多く、言葉の言い回しが古くて読みづらくわかりにくい
- 従業員が社内の管理体制について内部告発するのではないかと不安を持っている
尚、各種助成金の申請の際にも就業規則の添付が必要となりますので、作成しておくことが望まれます。
就業規則を活用すると、次のようなメリットがあります。

- 就業規則に経営理念や経営方針を反映して社長の代弁ツールとして活用できます。
- 規定の明確化により、社員が安心して働ける環境をつくり、公平感もうまれ、やる気もアップします。
- トラブルが起こらないよう事前のリスク回避になります。
- 引き継ぎ規定をつくるれば、いきなり退社する社員を減らすことも可能です。
- 退職・休職・解雇規定をつくっておくことで、社員が辞める時のトラブルが激減します
就業規則作成上の留意事項について

※ 労働者への不利益変更は、合理的な理由がない限り認められません。
最初から慎重に作成することが必要です。
※ 雇用形態別に作成しないと、正社員を対象に作成した就業規則がパート社員にも適用されます。
例えば、退職金の規程がパート社員にも適用されることになります。
※ 法改正がたびたびありますので、変更することが大切です。
就業規則の作成義務
常時10人以上の労働者を使う会社には就業規則の作成義務があります。
では、ここでいう「常時10人以上の労働者」とはどのような従業員でしょうか。
労働者の数が、一時的に10人未満になることがあっても常態として10人以上であれば、事業主は就業規則を作成しなければなりません。
この場合の「労働者」には、正社員はもちろんのこと、パートやアルバイトや嘱託社員の皆さん等も含めたすべての労働者とされます。
ただし、派遣社員に関しては派遣元の会社の従業員になるので、派遣社員を受け入れている派遣先の会社では労働者には含めません。
就業規則作成義務がある会社がその義務を果たしていない場合は、労働基準法違反になり、30万円以下の罰金が課されます。
労働基準法第120条 (参考)
では、労働者数が常態として10人未満である会社には、就業規則は必要ないのでしょうか?
確かに、労働基準法上は就業規則を作成する義務はありません。
しかし、事業主と労働者との争いごとを未然に防ぎ、職場の雰囲気を良くしてモチベーションを上げるという就業規則の役割から考えて、就業規則は是非とも作成しておきたいものです。
就業規則を定めていないがために、問題や事故が発生するケース多くあります。
この問題を未然に防ぐ為にも、就業規則作成の義務が課されていない会社であっても、就業規則という強い武器を作成することが良いと言えます。
就業規則活用までの流れ

1.メール・FAX・電話にて日程のご予約
当事務所からの訪問日のご予約をしていただきます。
ご相談は、初回は無料となります。
2.現状把握・ヒアリング・ご相談
社内書類を集めて、分析します 。
貴社に何度かお伺いし、貴社の状況を把握させて頂きます。
就業規則が法律や会社の現状に合っているか等を分析します。
3.お見積りの作成
就業規則、諸規程のお見積もりをメール又はFAXでお知らせいたします。
4.ご契約
5.企業経営理念・経営方針の確認
独自の社風、経営者のビジョンや、経営方針を就業規則に反映させるために、内容を確認します。
実情に合った就業規則となるように、慎重に行っていきます。
6.就業形態を再チェックして労働者を分類定義する
就業体系(就業時間、休日、その他取扱)の異なる労働者(正社員、パートタイマー、アルバイト等)ごとに区分し、就業規則を作成します。
労働条件の異なる労働者に同一の就業規則を適用してしまうと、トラブルの原因となります。
7.過去や今後の労務管理上の問題をチェックします
これまでトラブルになった、判断に迷った労務管理上の事例を洗い出します。
残業問題、賃金、休職など現在心配していること、改善したいと思っていることを挙げておきます。
8.構成の決定
労働条件や就業規則をどのように構成するかを検討して決定します。
解釈に誤解が生じないように、就業規則の条文で使用する用語を統一します。
9.就業規則の素案の作成、事業主代表へ素案の提示、説明、修正。
修正は複数回、お客様が納得のいくまで行います。
10.リーガルチェック、記載事項の漏れを確認
絶対に必要な事項が書かれているか、任意で定める事項に記載漏れが無いか、記載漏れや法違反、会社の実情に合わないものがないかなど、検討しながら作成します。
法改正があった項目、労働時間や賃金の計算方法などには特に注意します。
11.就業規則の原案の説明と決定
試案を、きちんとした条文形式にします。従業員にとって、わかりやすい具体的な表現で作成します。
労働者への説明などにより就業規則の内容を最終的に吟味し、必要があれば修正を行ない、最終的な就業規則に仕上げます。
労使協定が必要なものをチェックします。
12.必要な労使協定の整備
作成した就業規則の内容によって、使用者と労働者の代表者との間で、労使協定を締結しなければならない場合があります。
また、労働基準監督署への届出が必要なものもありますので、確認して作成します。
13.労働者代表の意見聴取
労働者の過半数を代表する者を民主的に選出して意見を聴取し、それを意見書として書面にしなければなりません。
決定した労働者過半数代表者に就業規則を読んでもらい、渡した意見書に意見とサインを書いてもらいます。
意見書とは、意見を聴くものであり、法律上は必ずしも同意を得る必要はありません。
しかし、今後のトラブルを避けるためにも、話し合いの場を設け、従業員側に納得してもらうべきでしょう。
14.就業規則の完成
まだこの段階では、法律上は有効なものとは認められません。
届出と周知が必要です。
表紙になる就業規則制定届を2部作成し、会社印を押します。
15.労働基準監督署への届出
就業規則、別規定、労使協定、意見書を、管轄の労働基準監督署へ届け出ます。
管轄の労働基準監督署へ正副2部を届け出ます。副本は会社で保存します。
16.労働者への周知
作成した就業規則は、直接配布、掲示板への掲示等、労働者全員が閲覧できるようにしておいたり、説明会を開くなどの方法で周知しなければなりません。
就業規則の労働者への周知を怠ると、就業規則の効力は発生しません。
※ 等事務所では必要があれば、オプションで従業員説明会も開催致します。
説明会の実施は、周知の証明にもなり、後日、紛争が起こった際にも、会社側に有利になります。
※ 状況にもよりますが、等事務所では通常、就業規則作成・変更のご予約から完成・届け出・周知と一通り終わるまで2カ月~4カ月程度かかります。